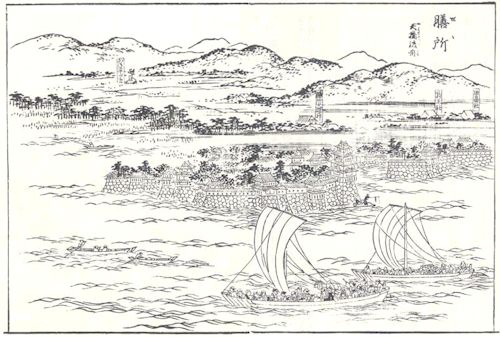|
膳所城 |
琵琶湖にかかる瀬田の唐橋は東海道, 中山道に通じ, 源平時代より東西をつなぐ要所であった
信長, 秀吉が琵琶湖ネットワークを作ったのと同様, 徳川家康が第一弾に取りかかったのが, この膳所城である
大津城が近くの山からの射程距離に入るため, ここ膳所に築城されることになった
設計はやはり築城の名手藤堂高虎
城主は戸田,本多,石川と続いた後再び本多家の所有となり明治を迎えた
明治維新の際には全国に先駆けて廃城した
城趾の遺構はほとんど残っていない
湖中に石垣を築いて建てた水城 本丸と二の丸の間には廊下橋でつながれており, 本丸は四層四重で各郭に櫓があったため その美しさは日本一といわれ「近江名所図絵」にも描かれている
本丸郭内には建築物などは何も無かった
美しかった水城も次第に荒れていき,江戸中後期には狐狸が住まうほどの荒れようであったという
明治の廃城とともに破却
城門は各所に移築
膳所神社(膳所一丁目)表門が、本丸大手門
篠津神社(中庄一丁目)表門が、北大手城門
以上重要文化財
近くには義仲寺(芭蕉庵)
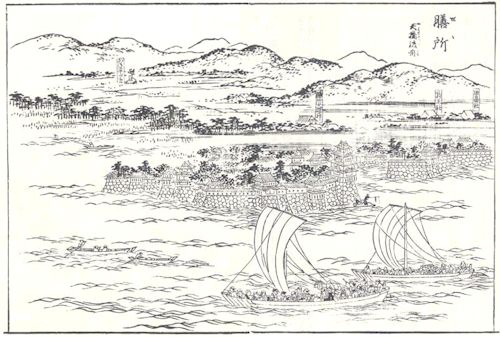 | 近江名所図絵の膳所城 |
 |
義仲寺 芭蕉庵 |
 |
膳所神社北門
もともと膳所城の東郷長屋門だった |
 |
膳所神社正門
膳所城の大手門 |
 |
篠津神社表門
膳所城北大手門 |
 |
膳所城址公園の入り口の門
城門風にしてあるが,現存や復興門ではない |
 |
 |
 |
本丸天守台の石垣
四層四重の天守が湖水にそびえる水城だった |
| 標高 |
|
| 比高 |
|
| 場所 |
滋賀県大津市本丸町7
|
| 最寄り駅 |
京阪石山坂本線 膳所本町駅 |