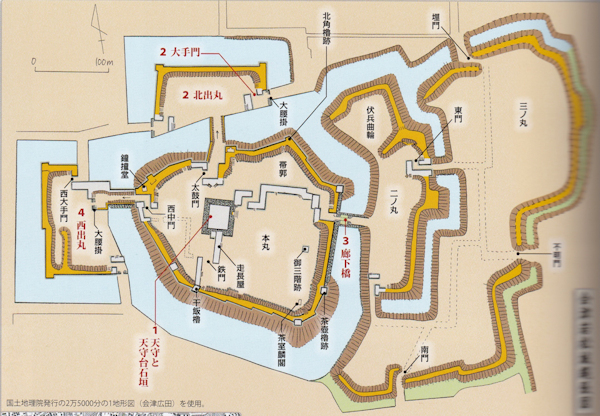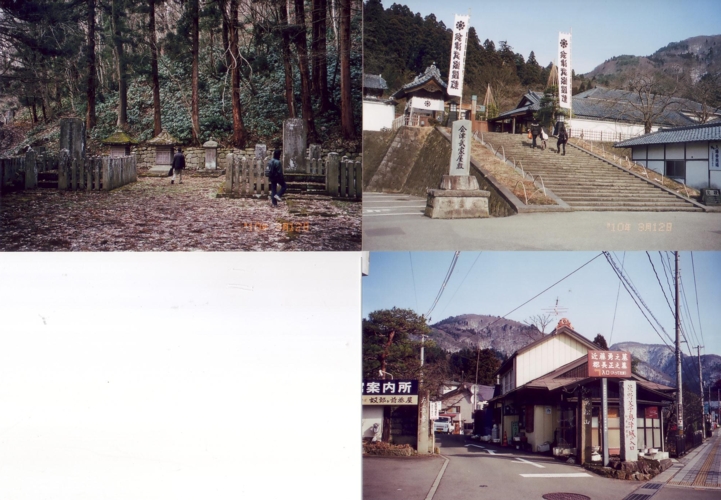|
会津若松城(鶴が城) |
初めてこの城を築いたのは,葦名直盛である.
その頃は黒川城といった
天正十七年(一五八九)に伊達政宗が葦名氏より摺上原の戦いで勝利した結果,蘆名氏を滅ぼした
この城を攻め取ったが, あまりに粗末な城だったようで, 家臣達が「このように小さく粗末な城では外聞も悪いから普請するように」と進言すると,
「おれは好機が到来したならば関東に押し出ていくつもりだから,こんな粗末な城を普請するつもりなど毛頭無い, それより軍律と軍費の捻出こそ当座の急務だ」と正宗が言ったとか
小田原討伐の後,秀吉により会津は没収, 伊達政宗は岩手県岩出山城(岩出沢城)58万石に減らされた
その後, 会津百万石は蒲生氏郷に与えられる
氏郷は百万石にふさわしい城にすべく, 会津若松城の縄張りを行い, 黒川と呼ばれたこの町を若松と改め, 城を鶴が城と命名した
氏郷死後, 嫡子の秀行は幼少なため会津を守るには不適だとして, 慶長三年,には上杉景勝が入る.
この時, 直江兼続は若松城の西方に神指城を築城し始める
が,関ヶ原の後, 上杉は米沢に移封にされ, 蒲生秀行が六〇万石で再び入城する
その後,蒲生忠郷は痘瘡(天然痘)で死亡し,蒲生家は断絶, 加藤嘉明が入城する
慶長二十年(一六四三)加藤明成は徳川に領地を返上,会津若松城には家光の異母弟,保科正之が入城した
この保科氏は三代正容の時,幕府の名により,松平姓に改姓するが, 会津藩主として代々続き, 明治を迎える
会津藩は最後まで幕府軍として新政府軍に抵抗し,戊辰戦争の時には,最新式の四斤(ポンド)砲でぼろぼろになったが,なお燃えず崩れず,鶴が城の頑丈さが示された
近くには,会津松平家代々の墓,白虎隊自刃の地の飯森山,会津武家屋敷(幕末の会津藩の家老西郷頼母の屋敷だった),
日新館(会津武士道をたたき込んだという会津藩の藩校),国指定名勝御薬園,歴代会津松平藩主の墓など, 観光地には欠かさない
会津若松駅からも観光地を回るバス(はいからさんetc)がたくさん出ていて, 移動も快適である
会津若松城周辺観光サイトへ
城の構造
蒲生時代には7層であったが,会津地方の大地震で崩れ,加藤時代には5層になった.
現在の復元天守は, 明治の古写真を元に復元された物で, 加藤時代のものと思われる.
今も堀,石垣,土塁などが残る
 |
左上
|
右上
|
| 左下 |
右下 武者走り
|
 |
南走り長屋 天守台より |
 |
廊下橋 二の丸より本丸を見る |
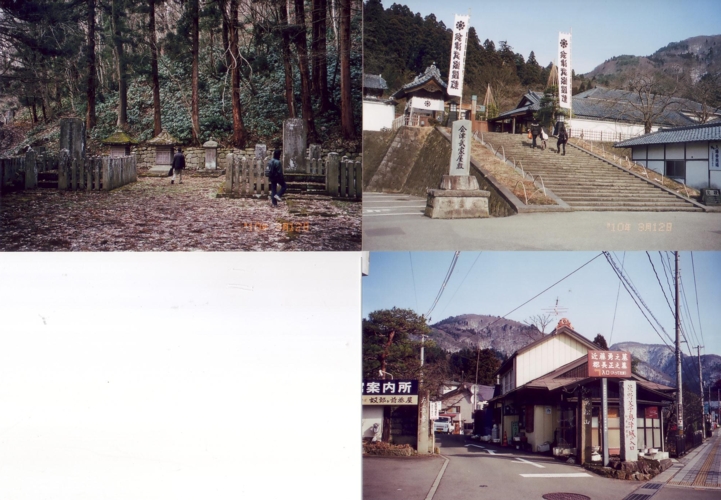 |
左上
歴代会津藩主松平家の墓
容保の墓もある
|
右上 会津武家屋敷
幕末の会津藩の家老西郷頼母の屋敷だった
この息子が黒沢映画の柔道家姿三四郎のモデル?
|
| 左下 |
右下 近藤勇の墓
新撰組近藤勇は板橋で処刑されたが,
逃げ延びる土方が,途中でこの地に
遺髪を埋めたという
|



 |
上 御薬園
歴代藩主が薬草を栽培した庭園 |
 |
下 白虎隊記念館
旧幕府軍に忠誠を誓う二十人余の少年
達が,城下からの火を鶴が城落城と誤認しここ飯盛山で
自刃した |
| 標高 |
|
| 比高 |
|
| 場所 |
福島県会津若松城追手町 |
| 最寄り駅 |
JR磐越西線会津若松駅からバスなど |